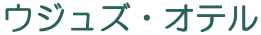
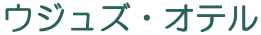
バスは夜中の十一時過ぎにイズミルに到着した。係員に尋ねると一緒になってオトガル中を探し回ってくれたが、どうやらベルガマ行きのバスは翌朝までないようだった。
イスタンブール、アンカラに次ぐトルコ第三の都市、イズミル。工業都市として名高いこのまちに寄るつもりは当初全くなかったのだが、接続便が終わっているとなればここで一泊するよりほかない。
私は外周をぐるりとまわって乗り場を探し、セントルムへ行くというドルムシュをつかまえると乗りこんだ。
乗客は徐々に減って行き、辺りの風景はとても大都市の中心街とは思えないものに変貌していった。本当にセントルムに向かっているのだろうか。
だが疑ってみてもしかたがなかった。私はこのドルムシュに身を委ねるしかないのだ。
「セントルム」
暗く細い道で車を停め、運転手がこちらを向いて言った。ここがセントルムだって?こんな閑散とした怪しげな雰囲気のところがセントルム?とはいえ、ついに最後の乗客となってしまった私は、ここで降りないわけにはいかなかった。
ドルムシュが走り去ると、辺りは静まり返ってしまった。通りは薄汚れて暗く、家内工業の工場のような建物が点在し、ところどころに労働者たちがたむろって煙草を吸っていた。
愉快な場所ではなかった。どちらかといえば不快で不安な場所だったと言ってもいい。こんな時間に、こんな場所をバックパックを背負った旅行者が歩くのはよほど奇異なことらしく、私は彼らの刺すような視線を感じながら歩いた。
 |
明日は早いんだ。さっさと宿を見つけて寝てしまおう。こんなところをうろついていたってロクなことはないぞ。
ところがそういう時に限って宿が見つからないのだ。表通りに出ても裏道に入っても、ゲストハウスやペンションの看板は全然見当たらなかった。もうドルムシュも走っていない。あとは方向もわからぬままひたすら歩きつづけて寝床を探すしかないのだろうか。
そのとき、道端の労働者グループから一人の男が抜け出し、近付いてきた。私は無意識のうちに身構えたが、笑いながら話しかけてきた彼の目を見て警戒を解いた。とても悪意がありそうには見えなかったのだ。
「メルハバ!ジャポン?」
空気は重く湿っていたが、男の挨拶は陽気だった。彼に頼っても大丈夫かもしれない。
「オテル(ホテル)!オテル!」
私は言ってみた。とにかく宿が見つからないことにはどうにもならないのだ。
「オテル?」
「エヴェット!」
男は嬉しそうに案内を始めた。ところが彼はためらうことなく立派な建物の中に入っていこうとするのだ。見上げればそれは四つ星ホテルだった。
ちょっと待った。ちょっと待ってくれよ。この建物なら私だって気づいていた。どこを探しても、場違いに立派なこのホテル以外見つからないから困ってたんじゃないか。
私は急いで単語を調べて言った。
「ウジュズ(安い)、ウジュズ・オテル!」
「ウジュズ?」
何だよそれを先に言ってくれよという顔をした男は、ついて来いというなり早足で歩き出した。
これはいいぞ。きっと適当な安宿を紹介してくれるんだ。
場末の臭いがぷんぷん漂う薄汚い一角に立つ古い建物の、一見それとはわからないような入り口を入り、私たちは緩い階段を上っていった。ところが入り口のドアを開けようとしたところで、彼はいきなり私の肩を掴むと必死の形相でなにやら説明を始めたのだ。
全身を使ってのパフォーマンスと熱意のこもったトルコ語とから、私は次のような内容を理解することができた。
「ここは危ない奴らの寝起きする宿だ。本当にヤバい奴らが多いんだ。しかも大部屋に雑魚寝と来たもんだ。だからおまえは寝るなり財布をすられちまうんだよ。サっとな。ほら、こんなふうに、サっとだぜ。へへ、どうする。ここで寝るか?俺はあんまりお勧めしないね」
ここなら安そうだ、と喜び勇んでいた私だったが、一瞬で萎えてしまった。あんたは一体なんなんだ。ここまで連れてきておきながら、お勧めしないだって?
そうまで言われて、敢えて危険を冒そうという気にはさすがになれなかった。私は他に行こう、といって外に出た。
 |
次に連れていかれた宿は辛うじてオテルの看板を掲げているところだったが、その古いことといったらさっきの宿泊所と大差なかった。そしてロビー(これをロビーと呼んでもよければ、の話だが)に入った私を、尋常ではない光景が待ち受けていたのである。
暗く埃っぽい部屋の四辺に、もう人生には何の希望も持っていないというような風体の、肉体だけは屈強そうな男たちがずらりと座り、無表情かつ無感動な目でじっと私を見つめていた。それはまるで目の前にちょっと気に入らない置物が置いてあるとでもいうような視線だった。
そこはなんとも居心地の悪い奇妙な静けさに満ち、例え五分後に世界が終わろうともわしには関係ないといった様子のフロントの親父は一人、隅に据えられた色のないテレビを見上げていた。そして誰一人、言葉を発しようとしなかった。
とにかく私は疲れていた。
「オーケイ、ここにしよう」
彼はいそいそと親父と交渉をしに行った。この外国人が宿がなくて困っている。泊めてやってくれないだろうか。そんな話をしているようだった。
親父は実につまらなそうに部屋の鍵を渡してくれた。いくら危険なにおいに満ちた宿であろうと、どれほど親父が無愛想であろうと、個室に入ってしまえばこっちのものだ。
部屋に入った私が男に礼を言い、ドアを閉めようとした瞬間のことだった。彼は俊敏に私の部屋に滑り込むと、後ろ手にドアを閉めたのだ。
おい、と私は思った。だが彼が口を開くのが先だった。
「いいか、ここは危険な宿だ。おまえが寝ている間におまえの物を盗みに来る奴がいる。おまえの財布を、こうやって抜き取るんだ。そっとな。だからよく聞け。俺が出ていったら、すぐに鍵を閉めるんだ。すぐにだ。さもなければ、財布を盗まれるんだよ。おまえの財布をな」
やれやれ、ここもさっきと一緒なのか。そういう宿なら鍵を閉めたとしたって気休めにしかならないじゃないか。でも、そうだとするとあのフロントの親父は…。おまえはそれを知っていて私をここに案内したのか?
私は何を信じればいいのかわからなくなり、次いですべてが面倒に感じられた。とにかく寝よう。
「わかった、わかったよ。もう私は寝る。だから悪いが出ていってくれないか?」
「鍵を閉めるんだ。すぐにな!」
男はそう言い残すと帰って行った。最後までわけのわからない男だった。
 |
部屋に入る前にちょっとだけ覗いてみた共用のシャワールームは却って体が汚れてしまいそうなおぞましい代物だったし、何より私は男の言葉を聞き、明るくなるまでこの部屋から一歩も出ない決意を固めていた。
なぜか明かりのスイッチは部屋の外側にあったのだが、そうしたわけで電気を消すのもやめることにした。
私は汗でべたつく体を、ここしばらくシーツの取り替えられた形跡のないベッドに横たえた。今にも崩れ落ちてきそうな染みだらけの天井と、黄ばんで割れて外れかかった洗面台が一つ。
財布を抜き取られるシーンが頭の中で渦巻き、今宵ばかりは貴重品を抱いて眠ることにした。
私がこれまでの旅路を回想していたときのことだった。
ドンドンドン!
ノックの音がした。さてどうしたものか。
ドンドンドン!
「どなたですか?」
私は外にいる誰かに尋ねた。我ながら実に無意味な問いかけだ。英語なんて通じるわけないのだから。
ドンドンドン!
私はもうどうでもよくなっていた。なるようになれ。
鍵をあけると、ドアの前にはフロントの親父が立っていた。親父は私を見てなぜかにっこり笑うと、そのまま静かに去っていった。
私は再び鍵を閉めた。そしてベッドに横になり、冷静に考えてみた。この宿は変だ。なんだかよくわからないけど、変だ。変なことは確かなのだが、疲れがそれに勝った。私が混乱した頭のまま深い眠りに引きこまれようとするまさにその時だった。
パチン!
部屋の明かりが消された。そして外には人の足音。
怖かった。一人で旅をしていて、初めて怖いと思った。どうしよう。どうすればいいんだろう。どうすれば―。
翌朝目が覚めると、身の回りには何の異変もなかった。明るくなってみると、昨日の出来事が現実にあったことなのかどうか確信が持てなくなってきた。でもあれは確かにあったことなのだ。その証拠にほら、明かりだって消えている。
私は荷物をまとめると、恐怖の館から逃げるようにチェックアウトした。フロントの親父は、最後まで一言も喋らなかった。