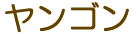
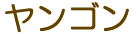
人々も寝静まった深夜に到着したため昨晩は気づかなかったが、一歩外に出てみると、そこは都会だった。
都会。だがスーツを着てアタッシェケースを持ったビジネスマンが闊歩する姿は見当たらない。きれいに刈り込まれた街路樹もなければ、丸いごみ箱も、真四角な電話ボックスも、タイルを敷いた歩道も、清涼飲料の自動販売機も、なにもかもがなかった。あるのはただ、混沌。それだけだった。
「ランド・オブ・コンフュージョン」だな、と私は思った。でも目前に広がるのはフィル・コリンズの歌声とは違って、クールでもなければ洗練されてもいない町並みだった。
 |
この国の郵便事情は悪い。政府による中身の検閲があるのはもちろんだが、その上で郵便局員によって美しい風景の写った写真を抜き取られたり切手を剥がされたりするために、国際郵便の届く確率は非常に低いのだ。それは、ミャンマー国内から差し出す国際郵便についても同じだった。
ミャンマーに行くのなら、ミャンマー人と結婚してヤンゴンに住んでいる学生時代の友達に渡してほしい。そう言って友人から託されたのがこのカードだった。日本からは全然連絡が取れないというのだ。
 |
通りを入ると、警察署らしき建物の入り口に、ミリタリールックに身を包み、マシンガンを抱えた警官が立っていた。看板には、ぐるぐる回るミャンマー文字の下に、"MAY I HELP YOU?"と書いてある。ああ、なんて親切な国なんだろう。
「すみません、このカードに書いてある住所に行きたいのですが」
「○×◇△…」
おっと、ミャンマー語で切り返されてしまった。この英語の看板はなんなのだ?とりあえず目指す建物がこの通りにあることはわかっていたので、あとはせめてどちらの方角であるかだけでも知りたかった。
「こっちですか、それともあっちですか?」
私はジェスチャーを交えて尋ねてみた。
「△◇×○…」
「じゃあ、こっちなんですね?」
私がある方向を指すと、警官は大きく肯いた。よし。
それぞれの建物の入り口には地番が振られていた。だが警官の指差した方向に歩いていくと、地番は目指すものから遠ざかっていった。やれやれ。
ミャンマー人はプライドが高い。人からものを尋ねられて知らないとは言えないらしいのだ。だから、知らなくても適当なことを教える。これが非常に性質が悪い。でもね、おまわりさん。自分の管区の、しかも自分の通りくらいわかっててよ。
しかたなく私は元来た道を戻り、警察の前を通り過ぎて更に逆の方向へと歩いていった。しかし該当する地番の振られた建物はどうしても見当たらなかった。引っ越したのだろうか。あたりをうろうろしていると、背後から日本語で声がかかった。
「日本の方ですか?」
「はい」
「なにかお探しで?」
「実はこの人を探してるんですが」
私はカードを見せた。
「私です」
偶然にも、買い物帰りの彼女が、正に私が探していたまり子さんだった。
 |
彼女は、日本に留学にきていたニュンさんと結婚してミャンマーに渡り、二年になる。ミャンマー語はぺらぺらで、東京で言えば銀座に当たるこの通りに部屋を買って住んでいる。私は夫妻の紹介で八十ドル分のFECを二万三千チャットあまりに両替すると、市内観光に連れていってもらった。
太陽が高く上るに連れ、気温はぐんぐん上昇した。東京は雪だと言うのに、この暑さはなんだろう。私たちは熱帯の強い日差しの中、溢れかえる人々の間を汗を拭いつつ歩いた。だが一歩日陰に入ると、そこには一陣の涼風が吹き抜けていくのだった。今は乾季である。
私はシュエダゴンパゴダやボーヂョーアウンサンマーケットといった名所を手際良く案内してもらい、地元の人しか知らないようないろいろな裏の事情や情報を教えてもらった。軍事独裁政権下での暮らしは楽なものではないようだったが、それでも皆うまく立ちまわって日々を生き抜いていた。そこらじゅうにスパイがいるから気を付けてね、と言われたものの、人々の表情には抑圧されて暗くなったり疑心暗鬼になったりする様子はまったく見うけられなかった。
パゴダとはミャンマー仏教の寺院に付き物の独特の意匠を凝らした塔のことで、中には仏像が納められている。それらの多くには目を奪うほどの金箔が張られていて、まばゆいばかりの輝きを放っている。ミャンマーがゴールデンランドと言われる所以である。
これら聖域においては、なんぴとたりとも履き物を履くことを許されない。靴下さえもだ。だからだろうか、ミャンマー人は誰もがゴム草履を履いている。そして忘れてはならないのが男女兼用の巻きスカート、ロンジーだ。ロンジーがどれほどポピュラーかと言えば、道路標識に描かれている人すらはいているくらいである。
私も、これからのパゴダ見物に便利なように、また少しでも暑さを凌ぐために、マーケットで三百チャットの草履とロンジーを買って身につけた。これでちょっと見には中国系ミャンマー人のできあがりのはずだった。実際、シュエダゴンパゴダにおいては、外国人のみ徴収される拝観料五ドルを巻き上げられずに済んだ。これはすばらしい。
私は夫妻に屋台でローカルな夕食をごちそうになり、困ったことがあったらいつでも連絡してほしいと言われて別れたが、あまりに観光旅行然とした一日に、なにかしっくりとこないものを感じていた。夫妻の親切はこの上もなく嬉しかったが、なにかが物足りなかった。
やはり旅は人に頼っていてはだめだ。翌日からは再び自分の力で切り開いていこうと私は決意した。
ミャンマーは電力事情も悪く、首都ヤンゴンでさえ停電が日常茶飯事である。この界隈もここ二日間停電だったらしい。その日の宿は夫妻に紹介されたホテルで、自家発電付きだった。ここなら安心だ。普通の部屋は十五ドルだが、六階なら上るのが大変なので十ドルでいいという。私は当然十ドルの部屋を選んだ。シャワー、トイレは共同で、やはりホットシャワーは水だった。
ところがその晩、どうしても寝付けない。体中、頭中がかゆいのだ。眠いほうが勝ったのであちこち掻き毟りながらなんとか眠ろうとした。どうせノミに決まっている。ノミなんているところにはいるのだ。気にすることはない。だが明け方近くなってどうにも我慢できなくなり、起きて電気をつけた。すると―。
何ということだ。ベッドは蟻の大群に襲われていた。私は急いで体中から蟻を払うと、もう一つのベッドで寝れば良いものを、シングル料金でベッドを二つ使っては申し訳ないという考えが朦朧とした頭に浮かび、蟻の踊るベッドに毛布を被せてその上で何も掛けずに眠った。
なぜ六階に蟻が?それはここがミャンマーだからだよ。私の内なる声が答えた。
 |
私は今回の旅に、計画らしきものを一切立てずに臨んでいた。それはこのような国では計画を立てること自体がナンセンスということもあったし、仕事が忙しかったということもある。だがなにより、成り行きに任せる旅というのをやってみたかったのだ。次の行き先にはいくつかの候補があった。そして、利用する交通機関にも。
思案の果てに、私は夜行バスでヤンゴンから六百キロ離れたミャンマー第二の都市、マンダレーに向かうことにした。
バスは、長距離を移動可能な交通機関の中で唯一チャット払いが可能な乗り物である。チャット払い可能とは、ミャンマー人と同じ料金と言うことを意味する。するとこの国の物価の安さが実感できる。ミャンマーには長距離バス会社が多数あり、私がホテルのフロント経由で予約したバスは三食付きで千八百チャットだった。なんと八百円しないのだ。マンダレーまでの所要時間は十六時間ほどとのことだった。
私がチケットを受け取りに行くべきバス会社のオフィスは、ヤンゴン中央駅前のスタジアムビルの中にあるという。ホテルのフロントは、ここから歩いていけるわ、と言った。そんなに遠くはない、と言う言葉が、結構遠い、という意味だとはその時は思いもしなかった。おかげで、オフィスについたときには指定の時刻をとうに過ぎていた。
オフィスはあたりに不釣り合いな近代的な新築ビルの中にあり、空調の効いた小ぎれいで殺風景な室内には大きなポスターが貼られていた。そこには輝ける新車のバスが誇らしげに写っており、"LEO EXPRESS"と大きなロゴが入っていた。
赤土舞うミャンマーの国土を、エアコンの効いたピカピカのバスの中でおやすみ中にひとまたぎか。悪くないな。
私は一人ほくそえんだ。うん。悪くない。