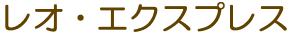
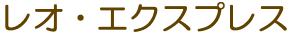
長距離バスターミナルは空港の近くにあった。私はタクシーをつかまえると、いつものように渋る運転手と散々駆け引きした上で、五百チャットでターミナルに向かわせた。三十分タクシーに乗って二百円なら、まあ良しとしなくてはならなかった。空港から市内へは足元を見た料金をいわれるが、市内からなら客のほうが強かった。
 |
ターミナルは、濛々と砂塵の吹き上がる広大な広場にあった。バス会社ごとに掘っ立て小屋のような待合室があり、ところどころ売店がある。あたりはおもちゃ売りの老人や、車内で食べるためのちょっとした食品類の売り子が歩き回っている。
私は、広場に無数にあるバスに一つとして新車がなく、市内を走るバス同様に日本車の廃車ばかりなのが気がかりだった。だが中にはきれいなバスもあった。それは岐阜市営バスだった。このくらいきれいならいいじゃないか。いやいや、あの伊豆箱根観光もなかなか捨て難いぞ。これならなんとか期待が持てそうだ。私は、駅前のオフィスで受けたイメージと現場との落差に戸惑いつつも、ともすればくずおれそうになる気持ちを必死に鼓舞した。
タクシーはレオの乗り場に到着した。我らがレオ・エクスプレスのバスは、我が輝ける新車は―。
ああ、やはり。それは相当にくたびれた日本製バスの廃車であった。私は荷物を預けるとバスに乗り込んだ。やれやれ、天井は剥がれかけ、エアコンは効かない。まあいい。六百キロ三食付きで八百円だ。世の中そう旨い話はないのだ。
乗客は八割くらいがミャンマー人、残りが白人のバックパッカーといった感じだった。この国を訪れる日本人はまだ少ないが、欧米ではメジャーな観光地になりつつあるようだ。私は最後列の一番端のシートを指定された。私の横にはバックパッカーのカップル、その横には中国系らしき女の子たちが座っていた。白人のカップルも女の子達もそれぞれで話し込んでいて、私が会話に入り込む余地はどこにもなさそうだった。私は特に中国系の手前の子が気になっていたが、ミャンマー語で話しているのだ。どうにもならなかった。
ミャンマー語は簡単な挨拶でもフレーズが長く、また拗音を多用する。そのため暗記はおろか、ふり仮名を読みながらの発音すら私にはとても難しく、今回は最初から諦めていた。英語で通そう。通らないところは身振り手振りで。それでなんとかなるだろう。ならない時は―。
その時はその時だ。
夕方四時半にバスは発車した。バスは「ハイウェイ」を北へとひた走った。ハイウェイがあるの?と昨日まり子さんに尋ねたのを思い出した。言葉だけよ、と彼女は言った。言葉だけ。実際そのとおりだった。ハイウェイといってもそれはちょっと広めのただの道路に過ぎず、しかもヤンゴンを離れるにつれ、道の状態はどんどん悪くなっていった。
しかし、道端にひろがる風景はスペクタクルというに足るものだった。集落は道路に沿って存在し、多民族国家ミャンマーらしく、それぞれの民族が、それぞれの衣装を纏い、それぞれの暮らしをしていた。そこには私の知らない世界があった。手を伸ばせば届く、すぐそこに。だがそれは、バスに乗っている私には決して触れることのできないものだった。私は遠い眼差しで彼らを見つめた。そう、彼らには彼らの暮らしがあるのだ。私はそれがどんなものかを知りたかった。ただそれだけを。
バスはやがてドライブインに到着し、夕食ということになった。ドライブインといっても道端にバラックがあり、その中でとてもプリミティブな食物が供されるというだけのもので、照明が暗いこともあって一同粛々と食事は進み、一時間ほどしてバスは再び発車した。
私たちのバスは、トイレ休憩でもないのに途中でよく止まった。その度に運転手たちはエンジンルームを覗いてあちこちいじっている。まあ廃車を使ってるんだ、仕方ないよな。私はもうただ無事にマンダレーに着いてくれさえすればそれで良かった。他には何も望まない。
だがそんなささやかな私の願いはかなわなかったのだ。
 |
比較的大きなまちで、バスは路肩に寄せられて止まった。また運転手たちが出ていく。なにやら雰囲気がこれまでとは異なるように感じられた。外からは大声が聞こえてくる。やれやれ。どうでもいいけどさっさと直して走ってくれよ。
外で交わされている会話を聞きつけたのだろう、ミャンマー人たちが様子を見に続々と降りていった。つられて欧米人たちも降りてしまった。残されたのは私と、同じ列の女の子達と、あと数人のミャンマー人だけだった。
バスの最後列座席はエンジンルームの上にある。様子を見ようとカーテンを開けた私の目に入ってきたのは、朦朦とすごい勢いで吹き上がっている白煙と、必死に消火器を使う男たちの姿だった。実は結構まずいことになっていたらしい。私は女の子たちのほうを向くと、言った。
「エンジントラブルみたいなんだけど…英語わかる?」
「ええ」
なんだわかるのか。これはラッキーだ。
彼女、李さんは英語名をミシェルといい、経済学を専攻する学生で国籍は台湾、十五までビルマにいたのだという。笑顔のとても素敵な女性だった。連れの女性、スノウ・ホワイトさんはビルマ時代の友人だろう。英語はできないようだった。
「トラブルは面白いよね」
私はそううそぶいた。
「そうね」
とてもそう思っていそうには見えない表情で彼女は答えた。やはり普通の人にとっては面白くないらしい。
「マンダレーに行ってどうするの?」
「マンダレー経由で他のところへ向かうのよ」
「ここは暑いけど、日本は今冬で、雪が降っているんだ」
「台湾も冬よ。でも雪は降らないわ」
私たちがそんなとりとめもない話をしているとき、いきなり大きな叫び声が聞こえた。今度はなんだろう、と思う間もなく、バスの中に残っていた乗客は私を除いて全員が一瞬のうちに猛ダッシュで車外に脱出していた。
ちょっと遅れて私も状況を理解した。きっと今の叫びは、ミャンマー語で「逃げろ」だったのだ。そうに違いない。
私も逃げた。
 |
外では、消火器だけでは足りず、今度はバケツで水が掛けられようとしているところだった。幸い炎上こそしなかったものの、もうバスは使い物になりそうにはなかった。おまけにこのまちは、ヤンゴンからわずか数十キロしか離れていないバゴーである。先が思いやられるとはこのことだ。
クルーがミャンマー語でなにやら触れ回っている。私はミシェルに尋ねた。
「ねえ、なんだって?」
「代わりのバスが一時間で来るらしいわ」
「そうか、じゃ、なんとか行けるわけだ」
せっかくのチャンスだったので、私は彼女たちを近くの喫茶店に誘って話の続きをすることにした。英語のできない白雪さんはちょっと嫌そうだったが、それでも誘いに乗ってくれた。
店に入ると、私は尋ねた。
「で、彼女はなんでスノウ・ホワイトなの?」
「雪みたいにキュートで可愛いからよ」
「君もね」
「ありがとう」
英語だと何でも言えるのが不思議だった。
ブン!急に辺りが真っ暗になった。ミャンマー名物の停電である。しばらくして自家発電に切り替わったらしく再び明かりがついた。
「いい思い出になるわね」
少し疲れた声でミシェルは言った。
一時間たったが、一向に代わりのバスは来ない。
「来ないよ、バス」
「この国では、一時間といったら二時間、一日といったら二日なの」
「それが普通のことなんだ」
「そういうことね」
まったく彼女の言う通りだった。ぴったり二時間後に、代わりのバスが到着した。
バスの座席は前と同じだったが、このトラブルで車内は一蓮托生のいい雰囲気に包まれていた。配られた毛布代わりのバスタオルをミャンマー人が頭に巻いたのを見て、私の横の白人がその真似をしたがうまくいかない。ミャンマー人は、そうじゃないんだこうなんだと言って説明する。言葉こそ異なっていたがお互いに通じ合い、車内は爆笑の渦に巻き込まれた。
今度のバスは恐ろしく冷房が効いた。
「寒いですね」
私は横の白人男性にそう話し掛けた。それがきっかけで会話が生まれた。
「ああ寒いね。きみ、仕事は何をやってるんだい?」
「コンピュータエンジニアです」
「仕事、面白い?」
いきなり鋭い質問を浴びせる男だ。
「え、仕事? うーん、そうですね、面白いです」
あえてここでつまらないと言うべき理由も見当たらなかった。だが、彼はあっさりとこう言った。
「俺はレジ係さ。退屈でやってらんないよ」
彼は国籍はニュージーランドだが、両親が英国人だという。私が英国に行ったことがあると言うとパートナーと一緒になって大いに喜び、そこから我々の旅行談義が始まった。私が、英国ではスカイ島とダラムが良かったですね、と言うと、そうだろう、あそこは最高だ、じゃああそこは、と言った具合で話はいつまでも続いた。
そのうち照明が落とされ、それぞれが眠りに就き始めた。だが、サービスのつもりなのだろうか、大音声でミャンマーミュージックのテープを流す。一曲終わってしばらくすると、また思い出したように次のテープを流す。隣の男が、くそっ、音楽を止めろ!と叫んでようやく静かになった。
相変わらず車内は底冷えがしていた。深夜であり、外も十分冷えているのだが、更に車内を冷やそうとする。誰もが頭上の送風口を閉じていたが、最後列は他の座席より高くなっていて、更に悪いことに私の席は端だった。そのため閉じた送風口から漏れ出てくる冷風をもろに受けていたのだ。それはどんな体勢をとっても避けることができない、さながら拷問のようなものだった。
私としては熱帯に来たつもりでいるから、服装は薄地一枚。日本国内での空港までの防寒用に唯一トレーナーを持ってきてはいたが、それもカーゴルームの中だった。配られた薄手のバスタオルは、この寒さから逃れるにはあまりにも頼りなかった。途中で二回、食事のための休憩があったが、食事をしても、私の席が寒いという事実にいささかの変化もなかった。
道はますます悪く、そして狭くなっていった。舗装してあるとはとても思えないような凹凸が至る所にあり、その上を構わずに飛ばすものだから縦ゆれが凄い。常時細かい振動に襲われるばかりでなく、しばしば激しい突き上げを食らって乗客の体が瞬間、一斉に宙に浮く。皆その時だけはオォ、などと声を漏らし、そしてすぐにまた眠りにおちて行く。だが私は寒くて眠るどころではなかった。仕方がないので前を見た。そして、心の平安のためには決して知るべきではない、時折やってくる激しい横ゆれの原因を知ってしまうこととなった。
道が狭いため、バスは真ん中を走っている。道幅自体は十分にあるのだが、アスファルトを節約してか、舗装部分だけが妙に狭いのだ。当然のように、向こうからこちらへやってくる車も真ん中を走っている。そして見る間に車間は縮まり、もう駄目かと私が身を固くしていると、対向車がウインカーを出し、こちらもそれに応じて急ハンドルを切ってよけるのだ。
信じられないことに、右側通行のはずなのに左側によけることがままあった。ウインカーが遅れたら、そしてよけようとした方向がたまたま同じだったら―。
考えてもしかたのないことは考えないに限った。結局ほとんど眠れないままマンダレーに到着した。トラブルのせいで、時刻はすでに十時をまわっていた。
 |
ターミナルに到着したバスを、いっせいに人々が取り囲んだ。皆ホテルの客引きだった。バスを降りると、私の名前が書かれたプラカードを持った男がいた。ヤンゴンの蟻ホテルをチェックアウトするとき、「マンダレーで宿を決めていないならここにしなさい、迎えにきてくれるから」とフロントが言っていたホテルからの出迎えだった。よしよし、出迎えご苦労じゃ。
私はミシェルたちに別れを告げると、オーストラリア人の女の子、ナターシャと一緒に迎えの車に乗り込んでホテルへ向かった。彼女ともいろいろ話してみたかったのだが、その時には深く会話する機会が見つけられないままだった。
今度のホテルは九ドルだ。良い傾向だ。どんどん安くなる。だが、果たせるかなここのホットシャワーも水だった。そこで試みに水のほうの蛇口を捻ってみた。すると、出てきたのはなんと冷水だった。ここに至り、私としてもミャンマーの安宿ではホットシャワーとは水、コールドシャワーとは冷水のことを指すのだと理解しないわけにはいかなかった。それが嫌なら一泊百ドルの宿に泊まりなさい、ということだろう。実際、そのクラスのホテルも少なからずあるのだ。私には無縁だが。