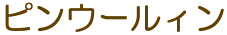
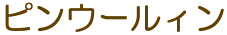
ピンウールィンは、ビルマ時代にはメイミヨと呼ばれていたまちで、マンダレーからは七十キロほど離れている。そこへ行くには、昨日のようにタクシーをチャーターするか、もしくはその路線や乗り場の複雑さ、特殊な乗車スタイルなどのため地元の人しか使えないともいわれる交通機関であるトラックバスに乗っていくしかない。
トラックバスとは、ハイラックスクラスの小型ピックアップトラックの荷台に木製のベンチシートと幌を取り付け、ものによっては更にその上にも荷台を組んで、人と荷物を共に満載できるよう改造して作られたバスのことである。ベンチシートに収まりきれない人は床に座り、そこも溢れると今度は荷台の最後部や外側部にぶら下がるような形で立ち乗りしたり、あるいは幌の上の荷台に乗ったりもする。その上更に、穀類や野菜、タイヤやテレビ、果ては生きた鶏や豚まで共に積載される。まさに何でもありの世界である。
楽なのは当然タクシーだった。だが私は地元の人の視点で、地元の人の生活が見てみたかった。私にとって、今やトラックバス以外の選択肢はありえなかった。
 |
私は流しのサイカーを止めると、ピンウールィン行きのトラックバスが出るというサファイアホテル前につけてもらった。だが、降り立ってもそれらしき様子はない。乗り場が変わったのだろうか。
あたりをうろうろしていると、先ほどのサイカーが近づいてきて私に尋ねた。
「どうしたんだ?」
「ピンウールィンに行きたいんだ」
「タクシーで?」
「いや、トラックバスで」
「トラックバスで!」
「そう。トラックバスで」
「…。まあ乗れよ」
促されるまま再びサイカーに乗ると、彼は現在のピンウールィン行きバスの乗り場まで連れていってくれた。そこには一台のトラックバスが停車していて、荷台に立った車掌が大声で、メイミヨメイミヨメイミヨ、と叫んでいる。確かにこれのようだ。
乗り込むと、私は空いていたベンチシートに座った。七十キロの距離を行くトラックバスの旅の始まりだった。
最初は空いていたバスも、マンダレー市内を走りながらあちこちで客と荷物を乗せていくうちに、いつしか立ち乗りも出るほどに混み合ってきた。大きな荷物は幌の上に載せられ、鶏を抱いた男はベンチシートに尻を押し込む。買い物帰りの老婆は床に腰を下ろし、都会的な装いの青年はひたすら眠りつづけている。そんな中に酔狂な外国人である私が一人、ぽつねんと座っているのだが、日本人と似てシャイな彼らが自分から話し掛けてくることはなかった。
なにしろトラックの荷台に木製の座席である。乗り心地は限りなく悪く、すぐに尻が痛くなってきた。幌はとても低く、中で立つことも体を動かすこともできない。それでも私はなんとなく嬉しかった。ロンジーとゴム草履を履いてトラックバスに乗っている。そして市民と一緒に遠いまちへ向かうのだ。
立ち乗りしている車掌は、バスが郊外に出たところで運賃の徴収を始めた。私は料金がいかほどかを知らなかった。きっとこの距離をタクシーで行けば数千チャットはかたいだろう。だが庶民の使うバスだ。もっと大幅に安くなくてはならない。私は期待を込めて二百チャット札を差し出した。足りないと言われればすぐに追加して渡せばいい。
車掌は釣りをよこした。返された金額は、なんと百七十五チャットだった。七十キロ、二時間半の旅が、お一人さま二十五チャット、わずか十円なのだ。
恐れ入りました。私は心の中でそうつぶやいた。
お昼過ぎにバスはピンウールィンに到着した。そこはのどかな田舎町で、観光客らしき者の姿はどこにも見当たらなかった。英国が開発したまちらしく、表通りに面した建物はどれも瀟洒で、道行く馬車も箱型のちょっとフォーマルなものだった。
私はレストランに入るとチキンの炒め物を注文し、手を洗わせてくれと頼んでみた。すると厨房の奥の裏庭で、店主は瓶から柄杓で薄緑色の水を汲むと、私の手に掛けてくれた。
ではこのような地区での飲み水はと言うと、井戸からドラム缶に汲んで運んでくるのである。そして商店で売られている飲用精製水は、ものによってはかび臭かったり泥くさかったりした。「化学的に純粋でpHは七」、「毎月政府機関で検査」。ラベルの謳い文句が虚しい。
通りを歩いてみた。平和なまちだ。車も少なく、馬車の蹄の音だけが響く。人々はゆっくりと歩き、商人も店先で昼寝。
木造の古い大きな建物があった。中では小さな子供たちが飛び回っていた。中の一人が私に気づくとこう言った。
「ハロー」
小学校の低学年に相当する子供たちを教える学校のようだった。彼らに話せる英語と言えばこの一言だけだ。私も応えた。
「ハロー」
通りに面した廊下で遊んでいた子供たちがたちまち集まってきた。口々にハロー、ハローと叫んでいる。私も無数に差し出される彼らの手を握り返して一人一人に返事をする。どこにこれだけの子供がいたのだろう。私は彼らに促されるまま教室の中に入った。まだ授業中だったのだろうか、先生はちょっと困った顔をしたが、それでもシャッターを押してくれた。そのうち部屋の中では身動きもできなくなってきたので外に出た。ところが校庭には私の後について、学校中の子供たちが集まってきてしまったのだ。
私は輪の中心にいて、百人を優に超える子供たちにもみくちゃにされながら握手を続けた。まったく、呆れるほどの大人気だ。外国人という、ただそれだけのことで。だが、それは決して気分の悪いことではなかった。
 |
ほうほうの体でそこを脱出すると、私はまちの散策を続けた。道端では親子が風呂敷きを広げて何かを売っていた。
「これは何?」
だが彼らは英語が分からないようだった。私が再び身振りで尋ねると、母親はその小さな赤い筒の一つをあけ、中に入っていた粉を指につけて舐める仕種をした。そして舐めてみろと私にも勧める。ハッカのような味のするその粉末は、どうやら清涼剤のようだった。
「ワンチャット」
唯一知っている英語なのだろう。これが一チャットか。それはあまりにも安すぎるように私には思えた。
私に用途を説明するために、大切な商品の封を一つ開けさせてしまった。私は財布から五チャット札(この国では硬貨は実質使われていない)を取り出して渡した。彼女は驚いて札を返そうとする。とんでもない、お金なんて。
私はまあまあとっておいてくださいよ、という感じでその手を押し返した。すると彼女は、あたふたと釣りを準備し始めたのだ。
「ありがとう」
私はそう言うと、そのままそこを去った。いいまちだった。
しっかりした一戸建ての立ち並ぶ一角で、裏門から私を見つめている老婆と若い女性がいた。私がそこを通り過ぎようとすると、二人はなにやら囁きあっていた。
「外人よ」
「どこの人かしら」
「日本人よ、きっと」
「日本人?」
たぶんそんな会話をしていたのだろう。ジャパン、というところだけが聞き取れた。ミャンマー語で日本のことをジャパンというのだろうか。私は立ち止まって挨拶した。
「こんにちは、いい天気ですね」
「こんにちは」
若い方は英語が少しできるようだった。私は尋ねた。
「ここでなにをやっているんですか?」
「私?私は主婦よ」
「立派なお宅ですね。一緒に写真を撮りませんか?」
私は老婆にカメラを託そうとした。だが、彼女は怖がってそれに触ろうとしない。私はまり子さんに言われた言葉を思い出した。
「ミャンマーの人はね、特に田舎に行くと、カメラなんて触ったこともない人のほうが多いの。だから誰かに写真を撮ってもらおうったって大変よ」
彼女は、旦那様を呼びましょうと言って家屋のほうに戻っていった。私もなんとなく後について裏庭に入り、勝手口に近づいていった。するとロンジーをはいてジャケットを羽織った、恰幅のいい紳士が現れた。どうやらここは、お金持ちの邸宅らしかった。
「こんにちは」
私はそれしか言わなかった。他に言うべき言葉があるだろうか。ところが紳士は、まあまあ入りなさい、といって私を応接室に招き入れてくれたのだ。
「コーヒーとお茶、どっちがいいかね」
「じゃあ、お茶お願いします」
「どこから来た」
「日本です」
「ほう、日本か」
紳士は戸棚からアルバムを取り出すと私に見せた。
「これが一番目の娘、これが二番目、これが三番目で次は写っとらんが男だ、そしてこれが四番目の娘だ」
「きれいな娘さん達ですね」
「そうだろう。これが二番目の娘の結婚式だ。そしてこれが四番目の娘の時のだ。こいつらは結婚すると日本に行ってしまった。日本のどこに行ったかって?それは知らん」
ひとしきり娘自慢をすると、紳士に代わって、写真には写っていないと言っていた唯一の男子で、恐らくは先ほどの女性の夫であろう青年が現れた。私は、若いと言うよりむしろ幼い感じさえする奥さんを呼び戻すと、三人で語り合った。
話が一息ついたところで、青年が私に尋ねた。
「ところで今日の宿はお決まりで?」
「残念ながら今晩マンダレーを発とうと思っています」
「そうですか。では、良いたびを」
きっと、決まっていないなら是非我が家に、と言うつもりだったのだろう。この家の家族には、そういう雰囲気があった。
私は世話になったことの礼を言うと、邸宅を後にした。帰り際、彼女は「あなたのことは決して忘れません。ピンウールィンを訪れるときは是非また遊びにきてください。あなたの友人、ヤスミーンより」と裏書きした絵飾りを私に手渡してくれた。通りすがりの外人に対して、それは望むべくもないほどの歓待であった。
 |
マーケットに行ってみた。そこはまちの人々の生活を支える食品や日用品の市場で、私は先々で好奇の視線にさらされた。
ある小さな間口の商店に集う人々から強烈な注目を浴びているのに気づいた私は、彼らに挨拶してみた。おいおい、外人が話してかけてきたよ、そんな様子で彼らは一斉にざわめいた。
「ここはあなたたちのお店?」
「いいえ、家です。私は教師をやっているの」
「じゃあ英語もできるんだ」
「ほとんどできないわ」
私が商店だと思ったのは小さな家だった。彼らの勧めに従ってその家の軒先に上がり込み、若い女教師、マさんを通訳にして私は質問攻めにあってしまった。私が答えるたびに皆はなるほどと納得した顔をする。そこには和やかな空気が満ちており、私も彼らと今会ったばかりだと言う気がしなかった。
その中の一人の男に写真を頼むと、彼は勇んでカメラを構えた。しかしそれは裏表が逆で、辺りは暖かい笑いに包まれた。
要するに、ここはそういうまちだった。
ピンウールィンには私の求めていたすべてがあった。至福の時を過ごした私は、マンダレーへの帰途につくことにした。もう日も傾いている。
帰りはタクシーにするという方法もあった。だが、せっかくだからまたあの不快なトラックバスに揺られて帰ろうと思った。あんなもの、もう一生乗ることがないかもしれないのだ。
ピンウールィンは高原のまちである。そのため、行きはワインディングロードを駆け上り、帰りは駆け下りることになる。来るときは苦しそうに聞こえたディーゼルエンジンの音も、今は軽やかに響いている。だが何しろ路面は最悪、路肩はぼろぼろ。崖を切り開いて作った道にはなんの落石対策も施されておらず、運が悪ければ転落して死ぬか、岩に当たって昇天だった。
そんなスリリングな道を、バスは快調に飛ばしていた。激しい振動にも慣れた私は、他の乗客と同じように軽く居眠りをしていた。そのとき、耳をつんざく爆発音と共に凄まじい砂塵が舞いあがり、バスはよろめきながら道の真ん中で急停車してしまった。あたりは林で、家もなければ人影もなかった。
爆発音は、タイヤの破裂によるものだった。旧式のトラックなのでタイヤはチューブ式であり、バーストが発生すると一気にぺしゃんこに潰れる。幸いにもその時、道は直線であった。ここが崖の途中だったらどうなっていたかについては考えたくもなかった。
降り立った乗客たちの様子を伺うと、誰も驚いたり困ったりした様子のものはおらず、またか、と言った感じで思い思いに煙草をすったり用をたしたりしていた。運転手と車掌は車体をジャッキアップして交換を始めた。だが上がり幅が足りないらしく、岩を拾ってきて下に敷いたりジャッキポイントを変えたりしながら、三十分ほどしてやっとスペアタイヤとの交換が完了した。
結局終点のマンダレーまで三時間かかった。
 |
夕食をとった私は、九時になるとホテル前でサン氏のタクシーを待った。しかし十分待っても来なかったため、サイカーを拾って駅に向かった。
マンダレーの駅舎は現在改築工事中で、彼が私を降ろしてくれた裏口は、さながら「ブレードランナー」で描かれたまちのような頽廃感の漂う、うら淋しい廃虚だった。どうやってホームに行ったものか。時間にはそれほど余裕がなかった。私がチケットを握り締め困っていると、近くの事務所から男が出てきた。駅の係員だろうか?
「どうかしましたか?」
「列車に乗りたいんです」
「どこ行きの?」
「バガンです」
男は私のチケットを持って事務所に引っ込むとその内容を確認し、ついてこいと言って歩き出した。しばらく行くと、建物の間からホームが現れた。
「向こうに停まっている列車がバガン行きで、こっちのやつは違うから。じゃ、気をつけて」
男は笑いながら去っていった。どうやら駅員ではなさそうだった。ありがとう、親切な人。
列車に近づいていくと、大きな声がした。
「アキラ!」
声の主は昨日の運転手、サン氏だった。私は彼への不満を口にした。
「ホテルの前で九時十分まで待ってたのに来なかったから、サイカーで来ちゃったよ」
「え?何を言ってるんだ。俺は九時にホテルへ行ったよ」
「だから私も待っていた。でもあなたは来なかった」
「俺はホテルに行ったさ。そしてフロントに聞いたんだ。昨日泊まっていた日本人を知らないかって。そしたら、もうチェックアウトしたっていうじゃないか。で、どこに行ったか聞いてみたら、さあ、知らない、って言うんだ。参ったよ」
「朝の九時だったの?」
「そう言ったろ?」
ねえちょっと。昨日の文脈からはとてもそうは読み取れないよ。だが私は一応謝った。
「それは悪かった。それでわざわざ見送りに?」
「そうだよ。どこに行ったか心配してね。ここに来れば会えると思って。バガンでの宿が決まっていないのなら、俺の友達のゲストハウスに泊まるといい。とても安いんだ。ここだよ」
そういって彼はカードを渡してくれた。彼もまた、純粋な親切で来てくれたのだった。
「君は寝る。君は起きる。そうすればそこがバガンだ」
私は心の中でサン氏の言葉を繰り返してみた。私は寝る。私は起きる。そうすれば、そこがバガンなのだ。すてきな夜行列車の旅になりそうだった。
発車までのあいだ彼と話をし、列車に乗り込んだ。元気でな、サンさん。