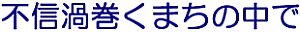
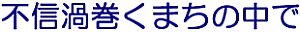
夜行チケットは当日の朝発売される。七時に起きて朝食をとった私は、ターミナルに赴いてマラケシュ行きのチケットを買った。ここの係員も英語を話す。
街の要所要所に英語のできる人間がいるので誰もが英語をしゃべるかのような錯覚に陥るが、実際話せるのはごく一部である。それでもこれまでほとんどアラビア語を使わずに済んでいるのは、いかに私が一般の人たちと交流してこなかったかを示すものだろう。
私はプチでブージュルードに向かった。約束のカフェに行くと、集まっていた少年たちが、アブドゥルはメディナの中にいる、と口を揃えて言う。基本的に英語を話す奴を信用しないスタンスをとっている私はそのまましばらくカフェで待ったが、彼らがあまりにうるさいので門をくぐってメディナに入ると、アブドゥルがいた。入り口には警官がいたので一緒のところを見られたくなかったのだろう。
ところが開口一番彼は言う。
「母が重い病気で病院に運ばれたんだ。すごく重い病気。だから残念だけど案内できなくなった。これから病院に行かなくちゃいけないから、昼の一時にここで会おうよ」
できすぎた言い訳に対し、私はかなりの疑わしさを感じずにはいられなかったが、口ではいたわりの言葉を投げ、一人でまわることにした。そう、それはそもそも私自身が望んでいたことなのだ。いいではないか。彼は、こことここがメインストリート。これらから外れなければ問題ないよ、と言い残して去っていった。
 |
自称ガイドに共通する行動として、まず相手を徹底的にもてなす、ということが挙げられる。ここでもてなすというのは、相手が喜びそうなところに連れて行くということだ。この少年も、アブドゥルが連れていってくれなかったところ、なめし皮職人地区ダッバーギーンやメディナを見下ろせる高台、青空市場などに私を案内してくれた。そしてなるほど気が利く、と思い始めたころに土産もの屋巡りが始まるのだ。
連れて行かれたのはレザークラフト、ハンドクラフト、金物屋、骨董屋。しかし今日の私は意志強靭であった。執拗な攻撃を尽く跳ね返し、その度ごとに少年は無口に、そして足早になっていった。ところが次に案内されたのはなんとアブドゥルが叔父の店だといっていたあの絨毯屋だった。
「ここには来たよ、昨日ジュラバを買ったんだ」
私がそう伝えると、彼は澄ました様子で言い返してきた。
「そうかい、じゃあミントティーでも飲んで絨毯を見てよ」
促されるまま中に入ると驚いたことにアブドゥルがいる。病院に行ったはずではなかったのか?彼とアブドゥルとはなにやらアラビア語で口論を始め、その結果アブドゥルだけが去っていった。さっぱりわけがわからなかったが、今はその件については考えないことにした。
絨毯は要らなかったが店のおやじとは顔見知り(彼らの言う「フレンドォ」)になっていたので店に上がってミントティーを頂く。しかしそういうコネクションがあるが故に、一旦上がると何も買わずに店から出るのは難しいと気づいたのは、お茶を飲み終えた後のことだった。
壁に絵皿が掛かっていた。四十五ディラハムと貼ってある。絵皿は買おうと思っていたのでこれにしようかと思案を始めた。いままで見て回った限りでは、紋様の描かれているものはあってもこのように風景の描かれたものはなかったのだ。
ところがおやじは私の視線を鋭く捉えるといきなり値札を剥がし、どこかへ捨ててしまった。また怪しい流れになってきた。皿の値段を聞くと二百七十ディラハムだという。私はたまげた。
「ちょっと!今貼ってあった四十五ディラハムは?」
「そんなのは知らん」
ただ呆れるのみである。
「いいや確かに貼ってあった」
「ではそれは横にある真鍮の皿の値段だろう。誰かが間違えて貼ったんだよ。真鍮の皿は機械製だが絵皿は手作りなんだ」
そう言うとおやじは絵皿の絵がいかに素晴らしいかを恍惚とした表情で語り始めた。
その頃には私も、このおやじが他のモロッコ商人の例に漏れぬ立派なペテン師だということに気づいてはいたが、四十五ディラハムの札は三枚ある皿のうちモノクロの一枚だけに貼ってあったので、カラーのものはもっと高いのかもしれないと好意的に解釈してやることにした。私が随分値引かせたつもりになっていたジュラバも、きっとたっぷりボられていたに違いない。いい気はしなかったが今更気づいても遅かった。
ともあれ、今回の四十五ディラハムの絵皿二百七十ディラハムは到底飲むことはできなかった。私は百ディラハムを提示した。おやじは心底悲しそうな顔で安すぎる、という。その頃には私はこの勝負を楽しむつもりになってきていた。
おやじはこれを機に一気に絵皿の在庫処分をしたいらしく、しきりに複数購入を勧めてくる。二枚なら五百ディラハム、三枚なら…というのだ。私は問題外だと突っぱね、終始一貫して一枚しか買わない、値段も百が上限だ、と言い張った。おやじもあの手この手で翻意を迫り、最後まで複数購入にこだわったが、私がどうやっても折れないと見ると結局諦めて一枚を百で譲るといってきた。私の完勝である。気分的には半額以下に値引かせたつもりであった。たとえそれがペテンであっても。自分は勝ったんだ、そう信じている限りは、信じられるうちは幸せなのだ。
彼らは日本や私の経済状態をとても知りたがった。航空券の値段や私の収入などについてである。しかし彼らの年収をはるかに上回る月給を貰っているとはとても言えないので「忘れた」と答える。「数百ディラハム(数千円)くらいか」、というので「たしかそんなもんだった」と答える。少し心が痛んだ。
 |
店を出ると、私はもう買い物はしたくないと少年に申し出た。そう最初にはっきりと断っておくべきだったのだ。しかしそれを聞いた彼は急に血相を変え、こう言った。
「さっき会ったアブドゥル、あいつはあんたのフレンドォか?」
「そうだけど」
「あいつは俺を突き倒した。この顎の傷を見ろ」
「へえ。それは災難だね」
一体それがどうしたというのだ。私の知ったことではない。すると彼はこう言った。
「あんたがあいつのフレンドォだというなら、落とし前として三十ディラハム払え!」
冗談じゃない。とんでもない言いがかりだ。
「おまえは私のフレンドォだと言っていただろう?それに金は要らないと最初に言ったじゃないか」
「ああ、たしかに俺はあんたのフレンドォだがアブドゥルは気ちがいだ。ハシシ(大麻)をやってる。あんたがそんな奴のフレンドォだというなら金を払ってもらうしかないね」
どうやらこの不良少年は初めから猫をかぶって観光客に近づいては、言いがかりをつけて金を脅し取ろうという算段だったようだ。
今回の旅で、初めて身の危険を感じた。よく見ればかなり目つきの悪い少年だ。断ればどういう行動に出るかわからない。だがこっちにも意地がある。額の多少の問題ではなく、最初に金は要らないといった奴に対してつまらない言いがかりに屈して金を払うのが我慢ならなかったのだ。
しかし奴は、呆れたことに私を案内した場所を列挙し始めた。そして私が奴に撮って貰った写真の枚数まで数え上げた。これだけのことをしてやったのだから金を貰って当然というわけだ。はめられた。私は不良少年にまんまとはめられたのだ。まさに計画的犯行だった。
だが地図なしでは出口に辿り着くのも難しいといわれるフェズのメディナである。その真ん中に一人取り残されたのではたまらない。
「おまえの話はわかった。わかったから、まずはブージュルードまで連れて行ってもらおうか」
「連れて行ったら必ず払うんだな?」
「まず最初に、ブージュルードだ。話はそれからだね」
「ふん」
完全に納得したわけではないようだが、奴は足取りも軽やかに迷路の中を進み始めた。私は奴を見失わないように追いかける。出口に辿り着くまでになんとか対応策を練らなくてはならなかった。
緊迫した空気の中で門に着いた私は、奴に向かってこう言い放った。
「いいかよく聞け、私はおまえに一ディラハムたりとも払う気はない。なぜならそれが約束だったからだ」
瞬間、奴の表情が変わった。私は急いで続けた。
「だが、私はおまえの案内には感謝しているんだ。その印としてこれを贈ろう」
私はアブドゥルから突き返された電卓をもったいぶって奴に渡した。三十ディラハムよりも電卓のほうが高かったが、年端もいかない子供からの脅しに屈して金を払うことだけはなんとしてでも避けたかった。
「これはこれ、金は金。ビジネスの話だ」
「じゃあ電卓は気に入らないのか?」
「いや、これはもらっておく」
「ならいいじゃないか」
「…せめてオレンジジュースをおごってくれよ」
一杯わずか二.五ディラハムのジュースだ。所詮は子供である。私はジュースをおごるといやいやながら奴と握手をし、別れた。
 |
つくづく憂鬱な気持ちになった。この時ほど切実に日本が恋しいと思ったことはなかった。早くこの嫌な街を去りたかった。私は足早にメディナを後にした。
そのとき、背後から駆け寄ってくるものがあった。振り返るとそれはアブドゥルだった。なぜ彼がそのように絶妙なタイミングで現れることができたのか、今にして思えば非常に不思議だが、そのときの私にそんなことを考える心の余裕はまったくなかった。そして彼の言葉がまたふるっていた。
「ねえ、いま幸せかい?」
「冗談じゃない。最悪の気分さ。なぜって?さっきの男はおまえのことを気ちがいだと言っていた。おまえはハシシをやる上にけんかを仕掛けてきたって」
彼は必死で弁明する。
「ハシシじゃない。ただのたばこさ。たばこなんてみんなやってるよ」
しかし昨日の夜彼がカフェで吸っていたものは、私にはハシシにしか見えなかった。更に彼は言う。
「けんかを仕掛けてきたのは向こうなんだ。あいつはナイフを持ってる。見てよ、この傷を」
そう言って彼は腕についたまだ新しい切り傷を見せた。そうか。そういうことであれば私も下手をすれば危なかったってわけだ。彼は、一人で歩くからこういう問題に巻き込まれるんだ、僕がついていれば安全だったのに、と残念そうに言った。
とにかくもうたくさんだ。一人にしてくれ。しかし彼はどこまでもついてきた。私が王宮に行くとお節介にも勝手に解説を始め、その後私を隣接する庭園に連れていくと悲しそうな目でこういった。
「どうしてあんな奴を信じるんだ。僕の言うことは信じてくれないの?」
私はもはやモロッコ人の言うことなど何も信じたくはなかったが、どちらかを信じろといわれればアブドゥルをとるしかなかった。彼はそれを聞くと安心したようにしみじみと家族のこと、この街のことなどを語り始めた。
さっき買った皿の値段を聞かれたので百と答えると彼は驚き、あんなの五十の値打ちだよ、と鮮やかに言い切った。やはりそうか。そんなことだろうと思ってはいたが、そうまではっきりいわれると値切った幸せも吹き飛び、腹が立ってきた。でもいいんだ。手作りであることは間違いないし、何より私は気に入ったんだから。押し売りされたのなら僕が返金させる、という彼を、私はそう言ってなだめた。
彼は言う。その皿を売ったのは僕の叔父ではないだろう、僕の叔父ならそんな酷いことはしないはずだ、と。そうだね、君の叔父ではなかった。私はそう答えた。しかしジュラバも絵皿も、私に騙して売りつけたのは彼の叔父だった。すべては金、金、金だ。はるばるモロッコまでやってきてこんな悲しい思いをしなければならないのはなぜか。それともそれは、ここがモロッコだからなのか。
私がすっかり打ち沈んでいると、彼は、今度こそ病院に行くので三時にブージュルードで会おうといった。私はウエストポーチから時計を取り出して時刻を確かめた。
ところが彼は、今度はそのワールドクロックに心奪われてしまったのだ。安ホテルに泊まっている私にとって、これは命綱だった。目覚ましがなければ朝早い列車にもバスにも飛行機にも乗り遅れるかもしれない。そういって私は必死に説得したが、彼はあれほど喜んだ腕時計を突き返すと、ワールドクロックを指差してありがとうと連呼し始めたのだ。
わかったわかった、午後に会うときに渡そう。私はそう約束して彼と別れたが、無論渡すわけにはいかなかった。ということは、もう彼とは会えないということでもある。もっとも私も彼のあまりの強引さには辟易していたので、敢えて再び会いたいとも思わなかった。
CTMは夜九時の出発だった。時間はまだたっぷりとある。せっかくの世界一のメディナだ。もう一度一人でゆっくり見ようではないか。私は重い足取りでメディナに戻った。しかしほどなく、こんな日本語が聞こえてきたのだ。
「ワタシハガクセイ、ニホンゴヲベンキョウシテマス、ニホンゴムズカシオカネイラナイ、ワタシハアナタヲタスケタイ」
棒読みである。振り返ると背の高い青年がいた。
「ハロー。君はガイドかい?」
「いいえ、私はガイドではありません。日本語を勉強しているがとても難しい。あなたは日本の方ですね?ぜひ案内させてくれませんか」
今度は流暢な英語で応えが返ってきた。怪しい奴め。
「残念ながら私は一人でまわりたいんでね、一人にしてもらえるかな?」
「ワタシハガクセイ、シンパイナイ…」
そんなやりとりをしながら歩いていると、嗚呼、なにが世界一の規模、世界一の複雑さだ。また今朝の不良少年に出会ってしまった。
青年と少年はアラビア語で激しい討論を始めた。どうせ私がどちらのカモであるかを決めてでもいるのだろう。少年はポケットから電卓を取り出して私を見やり、青年に向かってフレンドォがどうのこうのと叫んでいる。うんざりである。
そのうち話がまとまったらしく、不良少年がこちらを向いて微笑んだ。
「この男は僕のいとこだ。二人で案内するよ」
いとこ。今度はいとこですか。やれやれ、だ。いいか、私は ひ・と・り・に・な・り・た・い んだよ。一語一語区切るようにいってやった。すると奴らはこういうのだ。
「一人で行くのもいいだろう。でもとても面白いところを紹介するよ。と・て・も面白いところなんだ。一人でまわるのはそれからだっていいだろう?」
性善説の私はそういう言葉に弱い。こころを入れ替えて、何かものすごい見どころを案内してくれるとでもいうのだろうか。
「わかったわかった。そこに行ったら、それから後は一人にさせてもらえるね?」
「もちろんさ」
私は奴らについていった。途中奴らは写真を撮ってやろうか、と言ってきた。しかし脅迫の際に奴が言った、「写真を六枚撮ってやった」という言葉のショックも未だ覚めやらなかった私は、その申し出をきつく断った。奴は、心配ない、すでにプレゼントは貰った、これで十分だといって電卓を見せるが、誰がこんな奴を信じるものか。
だがそのときの私は、信じてもいない奴の言葉を信じてひょこひょこと一緒に行動しているということについての自己矛盾に気付いていなかった。そして連れて行かれた先は、「とても面白いところ」とは、これまででも最大規模の絨毯屋だった。糞食らえである。
 |
その店では日本語をしゃべるモロッコ人が登場した。私は久しぶりに日本語を話し、日本語ならではの細やかな表現で、いかに自分の経済力では絨毯が買えないか、帰りの航空券もこれから買うことにして窮状を訴えたのだ。無論、相手も日本語ならではのねちっこさで重箱の隅をつついてきた。そして私が断るたびに新しい絨毯を広げては、こう言うのだ。
「では、この絨毯はお好きですか?」
うずたかく積み上げられた絨毯を前にして、いよいよ私は最後の手段を使うしかなかった。
「実は絨毯は嫌いなんです」
「絨毯が嫌い?」
彼は一瞬唖然としたが、さすがはモロッコ商人だ。こう切り返してきた。
「あなたが嫌いでもご家族は好きでしょう」
「いや、家族も嫌いです」
「…。では、壁掛けは?」
「壁掛けも嫌いです。絨毯も壁掛けもマットも嫌いです」
今まででもっとも苦労したが、やがて私は店を出ることができた。店に入ったとき最初に、「ミントティーは砂糖入り、抜き、どちらがいいですか?これは絨毯買う、買わないのビジネスに関係なく、モロッコ流のおもてなしです」と日本語で説明されたミントティーは、遂に出てこなかった。
深呼吸をし、私が一人散策をしようと歩き始めると、またも奴らがついてきた。こいつらどこまでふざけた真似をすれば気が済むんだ?
「おい、ここを出たら一人にさせてくれるって言ったじゃないか!」
「いや、もう一件、もう一件だけ面白いところがあるんだ。今のところも面白かっただろう?もう一件だけ行ったら一人でまわればいいさ」
これまで我慢に我慢を重ね、頭の中で張りつめていた糸が遂にぷちんと音を立てて切れた。
おおい、そっちにいったらメディナから出るよ。もう帰るのかい、戻ってこいよ。そんな声を背に受けながら私はタクシーに乗り込んだ。もうこれ以上フェズにいなければならない理由なんてなかった。さらば、世界一のメディナよ。
新市街に戻った私は、カフェで時間を潰してからターミナルへと向かった。荷物の計量や預け方などのシステムはさっぱりわからなかったものの、なんとなくこなすことができた。バスの行き先表示はアラビア語である。当然読めないので、これもまわりの人に確認しなくてはならない。
乗り込むと、列車ほど汚くはないが決してきれいとも言えない車内にはテレビまで備え付けてあった。だが車内の照明は赤ランプと青ランプが交互に点いているという悪趣味の極致。しかもバスが発車して丁度眠くなってきた頃に始まったビデオは、大音声のアラビアン・コントであった。画面ではジュラバ姿の人々がなにやら動き回り、観客は大笑い。
私はすべてを受け入れ、眠りに就いた。