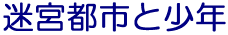
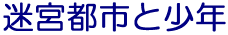
都市間移動には国営のバス(CTM)もあり、鉄道を使ってもCTMを使っても所要時間はほとんど変わらない。しかしCTMは全席座席指定であり、事前にターミナルへ出向いてチケットを買っておく必要があるため鉄道のほうが融通が利く。フェズへはCTMが十一時、鉄道が十時発であったため、やはり鉄道で行くことにして再び切符を買った。
駅で日本人青年と出会った。百万円を元手にすでに一年近く世界を放浪しているという。服装からして私とはサバイバル度が異なり、敬服する思いだった。同じ列車に乗り込んだ私たちがコンパートメントで話をしていると、自称サウジアラビア人が話しかけてきた。石油をやっていたというが中東の地名も言えず、かなり眉唾もののおやじだったが、例によって「俺は堺にフレンドォがいる」などと吹いて握手を交わして去っていった。
彼らの善良さをどこで見分けるか、また広げられた大風呂敷の中からどうやって真実を摘み取るか、実に難しいところだ。サウジおやじはいい奴のようだったが、「明日からあのおやじは、ヨコハマにアキラというフレンドォがいると言いふらすに決まってるよ」とサバイバル青年はいった。彼らにとってフレンドォとはそういうものなのだ。
 |
フェズに着き、私は彼と別れて新市街にホテルを探した。メクネスでの経験から、やはりホテルは新市街にとっておいたほうが面倒に巻き込まれたときに有用だと判断したからである。
チェックインを済ませた私は、今日こそリコンファームをしようとテレブティックと呼ばれる公衆電話サービス店を探して入り、店員に両替をしてもらうとサベナ航空に電話をかけた。しかし、やはり何回かけても通じない。一体どうなっているのだろう。
そのうちに私は気づいた。この国では昼休みが長いのだ。電話が繋がるには、結局三時近くまで待たなくてはならなかった。なるほど、所得格差も生じるわけだ。
モロッコでは東洋人は珍しい存在である。街を行けば多くの者が振り返り、声をかけてくる。最も多いのが、ヘイジャパン、コニチワ、のたぐいのひとことであり、次いで何処から来たんだ、日本人か中国人か、ようこそモロッコへ、といった英語での呼びかけになる。また彼らは日本人といえばカラテだと思っていて、いきなりカラテのポーズを仕掛けられることも少なくない。はじめのうちはにこやかに返事をしていたものの、最近は無視することも多くなってきた。新市街での声掛けには無害なものも少なくないが、メディナでは自称ガイドや売り子は言うに及ばず、それ以外であっても英語での声掛けには必ず何らかの下心があると疑ってかかってほぼ間違いない。
ホテル前で自称ガイドが声をかけてきた。何処から来たんだ?日本です。メディナを見るのか?そうです。ガイドしてやろうか?結構です。私は公認だぞ、なぜ断る?
自称ガイドのなかには自らを合法な公認ガイドだと称するものも少なくない。モロッコ人はみなIDカードを携帯していて、それをいかにも公認ガイド証であるかのようにちらりと見せる。もっとも、初めからガイドを雇うつもりなどない私にとってはどちらでも同じことだが。
予定では、今日と明日はフェズを観て、明日の晩の夜行CTMでマラケシュへ向かうつもりだった。フェズ~マラケシュ間は距離が長く、昼間に移動すると一日潰すことになってしまうからだ。そこで、まずは地図をたよりにCTMターミナルを探しにいった。しかしそこはすでに閉鎖されていた。これは困った。
隣にある民営バスの、今にも崩れ落ちそうなターミナルに行って何か手がかりはないものかと探していると、小汚いおやじが近づいてきて何処にいくのかと私に尋ねた。マラケシュだと答えると、マラケシュ行きはここではない少し向こうだ、ついてこいといっててくてく歩き出した。おやじ曰く、この古いCTMターミナルはしばらく前に閉鎖になって向こうに新しいのができたのだという。
おやじについてしばらく歩いたが一向に何も見えない。そろそろまずいかと思い始めたころ、やっと新築のターミナルが現れた。明晩の出発時刻を係員に確認し、おやじに礼を言って帰ろうとすると、たばこをくれ、という。ないというと五ディラハムくれ、と来た。
なるほど。この国に無償の親切なんてものはないってわけか。とはいえターミナルの場所を教わって助かったことは確かなのでチップを渡し、握手して別れた。今後はコスト対効果という観点でも気をつけねばなるまい。
ここからメディナへは数キロある。市街を走る乗り合いバスを探したが、適当な乗り場が見つからない。それではプチで行こうかと思ったが、空車が見つからない。困っていると、タクシーかい、と声が掛かった。明らかに白タクだったが、値段を聞いて考えようと思った。
「メディナまでいくら?」
「百ディラハム」
問題外だ。交渉できるレベルではない。いくらなら乗るんだ、と叫ぶ声を尻目に、私はメディナに向かって歩き出した。
フランスの統治を受けていただけあり、この国には「ヨーロッパ的なるもの」もそこここに存在する。新市街を中心に点在するオープンエアのカフェもその一つである。黒煙と砂塵の中、いい大人が平日の昼間から大挙して集まり、歩道に設けられたテーブルの上で四方山話に興じながら砂糖のたっぷり入ったミントティーをすすっている。一日五回のお祈りにカフェでのブレイク。いったい彼らはいつ働くのだろう。そんな疑問を抱きながら、昨日の出費を埋めるため、今日はカフェでパンとミントティーの軽い昼食をとることにした。いくら追い払ってもまとわりついてくる蝿が鬱陶しい。
私が焼き立てのパンを齧っていると、貧しい身なりの子供たちが集まってきて金の無心を始めた。一人にあげたらきりがないと思ったので可哀相だが無視する。おもちゃ売りや靴磨きも軽妙なリズムを取りながらやってくる。それらすべてに私は「拒否のジェスチャー」で応えるのだ。
 |
モロッコにももちろん信号はある。しかしまじめに守っている車は多くない。そして車線も引かれてはいるもののほとんど意味を成さず、少しでも空いていればそこに割り込んでくる。人は走る車の前を涼しい顔で横切り、車は人の列に平気で突っ込んでくる。そして彼らはクラクションを常用する。意味がなくてもクラクションを鳴らす。とりあえず鳴らす。なにがなんでも鳴らす。鳴らす。鳴らす。だから新市街は大変うるさく、そして危険だ。
だがそう思っているのは私だけのようで、混沌としていながらも不思議と統制の取れたその交通システムの中で、私はついぞ事故というものに遭遇することがなかった。
モロッコ人は皆メーター計算でプチに乗るが、観光客は交渉制。それはタクシー運転手が累進課金をするために編み出した方法なのだろうか。しかし私がのったそのプチはメーターを使ってくれた。おかげでいつもより安く上がったので、浮いた分はチップとして渡した。
さあ、遂に世界に冠たるフェズのメディナにやってきた。だがその象徴でありメインエントランスでもあるブージュルード門でタクシーを降りた瞬間の私を待ち受けていたのは、凄まじいまでの自称ガイド攻撃だった。
曰く、私は公認だから安心だ、俺なら二百五十ディラハムでガイドする、僕は学生で英語を勉強している、自分はハスラー(家に連れ込んでクスリで眠らせて狼藉を働くといわれる悪徳ガイド)ではない、などなど。全部で何人いたかは思い出せない。私は無視してしばらく歩いていたが、一向に引き下がろうとしない彼らに業を煮やして高らかにこう宣言した。
「私はガイドを雇うつもりなどない。一人でまわってみたいんだ」
しかし彼らはその一言を待ちかねていたかのように一斉に反論を始めた。
「一人で行くなんて馬鹿げてる。この中はとても複雑で危険なんだ。絶対にガイドが必要だよ。ガイドなしでは『ドロボー』に財布を盗まれ、挙げ句殺されてしまうぞ」
「殺される?」
「そうだよ、殺される。だがこの俺がガイドをすれば安全さ。料金は相談に乗ろう。百ディラハムでいい。ここにこれだけのガイドがいるけど、あんたが好きなのを一人選んでくれればいいんだ。一緒に行くのは一人だけだから。さあ、誰を選ぶ?」
 |
ところがガイド抜きでメディナの喧燥を楽しむ暇もなく一人の少年が現れた。彼の言い分はこうである。
「僕は日本人と友達になりたい。東京や大阪にも友達がいるんだ」
「へぇ、フレンドォね。それはよかった。ところで私は一人になりたいんだよ。一人にしてくれないかな?」
「ねえ、心を開いてほしいんだ。僕は英語の勉強をしたいだけ。金が目的じゃない。約束するよ」
金が目的じゃない?そういえば昨日の男もそう言っていたっけ。でも口で言われただけではそれが真実かどうか判別するのは難しい。だが少年は私の心が緩んだのを敏感に察知すると、ついておいでよ、といって勝手にガイドを始めてしまった。果たしてこいつは信用するに足る人間だろうか。まあ相手は子供だし、そう悪いこともしないだろう。私は彼についていってみることにした。
少年は名前をアブドゥルといい、十七歳だった。叔父が絨毯屋だという。きたきた、絨毯屋だ。これは警戒を怠らないようにしなくてはならない。彼はフェズのメディナの中でも見どころといわれているところを要領よくまわってくれた。そして叔父の店だという絨毯屋に、あたかも当然の如くやってきた。
ミントティーをふるまわれた私は、彼が持ってきたゲストブックを読まされた。欧米人の書き込みに混じって日本人のものもいくつかある。曰く、アブドゥルは本当にいい子で、私は彼のうちに泊めてもらいました。絨毯もどうしても買えないということを説明すれば納得してくれます。私はいくらのものをいくらにしてもらいました。などなど。ほぉ、どうやらお前は悪い奴じゃないらしいな。大変よろしい。
店のおやじは山ほど絨毯を出してきて自らの商品に陶酔した様子で説明する。しかし私はどうやってこの状況を脱するかということばかり考えていた。彼には案内してもらった恩義がある。ちょっとしたものなら買ってやってもいいが、絨毯は高すぎる。何万もするのだ。
壁に掛かっている茶色いジュラバに二百五十ディラハムという正札がついているのに気づいた私は、絨毯は高くて買えないけどジュラバなんかいいですね、といってみた。色を聞かれたので白がいいというと、あなたはついているといっておやじは上の階から白いジュラバを持ってきた。
「ここらに掛けてある二百五十ディラハムのものは観光客用で質が悪いが、これは高品質で四百七十ディラハムなんだよ」
おやじは自慢げにそう言う。一見色が違うだけであったが、私は素直におやじの口上を信じ、へえ、これはいいものなんですか、と言ってとりあえず三百ディラハムから値切り交渉を始めることにした。するとおやじは、おまえはわれわれ家族を殺す気か、と言って目尻を釣り上げた。おいおい、殺すはないんじゃないの?
私は、じゃあ三百二十、三百三十、という具合で進めていき、結局三百五十で商談はまとまった。だが商売上手なおやじは、その後チップの名目で私から十ディラハム巻き上げるのを忘れなかった。まあ四百七十ディラハムのものを百ディラハム以上安く買ったんだ、いい買い物をしたとその時は思った。
その後もおやじは、カードもトラベラーズチェックも日本円も使えるからといってしつこく絨毯を勧めた。そんなとき彼らが使う言葉は決まっている。「ビンボープライス」である。この言葉はメディナ内の随所で耳にする。誰が教えたか知らないが、ビンボープライスが特価という意味だとでも思っているのだろうか。ちなみに他にも活用形として「ファミリープライス」と「ラストプライス」というのが存在する。
私はジュラバがあれば幸せだと強く主張してその場を切り抜けた。絨毯屋相手もほとほと疲れる。向こうも一枚売れば大きいだけに必死なのだ。
店を出ると少年は、これから用事があるので一旦別れるが夜のメディナも素敵なので是非案内したいと言い、私は七時に彼と落ち合う約束をした。だが別れ際に彼は言った。
「僕にプレゼントを持ってきてね!」
そうか、やはりおまえもそういう魂胆だったか。でもまあいい、私には電卓がある。
 |
第三世界ではクレジットカード詐欺が多い。伝票に余分な一枚を挟んで複数の商品を購入したことにするのだ。今日は危うくカードを使わされそうになったが、そういう事故を防ぐため、また資金に余裕があると悟られるのを防ぐため、私はカードを財布の奥深くに隠した。
それにしてもフェズの街の強引さには参った。メクネスではモロッコ人と常に一緒に歩いていたためガイド攻撃にあわずに済んだということがあるのかもしれないが、商店の客引きひとつをとってみてもフェズのほうが断然パワーがある。ところが港町タンジェに行けば、そんな彼らでさえ可愛らしく思えてくるという。やれやれ、すごい国だ。
約束の時間の三十分前、私は再び街に繰り出した。しかしまたもやプチが全然つかまらない。これはそろそろまずいな、と思った私は料金交渉の際にアラビア語で答えてきたプチにOKといって乗ってしまった。背に腹は代えられない。
ところが到着していつもの相場十ディラハムを払うと、なにやら足りないと叫んでいる。ダメダメ、相場以上の金なんて払うつもりないからね。私は無視して走り去る。
待ち合わせ場所でぼんやりと待っていると、やはり多くのガイドが近づいてくる。だが、友達を待っているんだ、の一言でどのガイドも去っていった。きっとテリトリーというものを重視するのだろう。
しばらく待つとアブドゥルがやってきた。ブージュルード門近くのカフェでジュースを飲みながら世間話をする。彼は六カ国語ができるという。たいしたものだ。その能力を他に活かせばいいのに。そして私は今日のガイドの礼として、電卓を渡した。彼は学生だからこれで計算ができるよ、と喜んでくれた。
ところがその後、夜のメディナを散策しているうちに彼の態度が変わってくる。実は僕は時計を持っていないのでその腕時計が欲しい、というのだ。私は昨日と同じように理由を説明して諦めてもらおうとした。すると彼は明日も案内するからそれをくれというと、ついさっき喜んだふりをした電卓を私に突き返し、返事も待たずに「ありがとうフレンドォ」と連呼し始めたのだ。フレンドォという言葉を嫌いになりはじめたのはこの頃のことだった。
一旦贈ったものを返された私としては当然いい気分ではなかったが、時計もそう高いものではなかったので、今日のガイドの代価としては適当だろうと考え譲ることにした。そのとき、私の頭の中には目覚まし用として別に持ってきていた小型のワールドクロックのことがあり、それさえあれば腕時計がなくてもなんとかしのげるだろうと考えていたのだ。
その日の帰り際、じゃあ約束の腕時計を渡してくれという彼に、明日渡すよと予防線を張ろうとしたが、それでは明日の待ち合わせの時間がわからないと強弁されてしまい渡さざるを得なくなった。こいつも見掛けによらず手強い相手だ。だが時計を渡したからには明日もしっかり案内してもらわなくてはならない。明日はうちに招待するよという彼の言葉を信じて、私はホテルに戻った。
深夜、レストランを探しに新市街を徘徊すると、怪しい連中が出没していた。日本人の私に声が掛かるのは昼と変わらないが、その内容が、いいブツあるよ、のように大麻の取り引きを匂わすものに変わっていたのだ。まあ黙殺している限りは問題ない。
私はクスクス(小麦の粉を蒸して野菜や肉とあわせたもの)を頼んだがとてもまずく、ほとんど食わないまま帰って寝た。