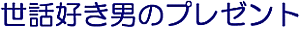
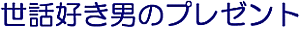
朝四時。外からのすさまじい大音声で目が覚める。
ムスリム(イスラム教徒)の国では至る所にモスク(イスラム寺院)が建てられ、礼拝の場となっている。イスラム教では一日五回の礼拝が信徒に課されており、時間になるとモスクに取り付けられた拡声器からありったけの音量で「祈りなさい」との叫び声が繰り返し流れ続ける。今はそのうちのひとつ、「夜明け前」であった。
通りを見下ろすとジュラバ姿のモロッコ人たちが歩き回っている。こぞってモスクに向かっているのだろう。不思議な抑揚を持ったその叫びを聞いているうちに、私はいつしか再び眠りにおちていった。
ホテルで朝食を済ませた私は、タクシーでメディナへと向かうことにした。
この国には都市内移動専用のプチタクシーと広域移動用の乗り合いタクシーであるグランタクシーとがあり、プチは観光客の場合料金事前交渉制、グランは近距離なら二ディラハム程度で遠距離なら交渉制である。プチはプジョーのツーボックス、グランはベンツが多く使われる。というと聞こえはいいが、その実体は他国で廃車になったものを持ってきた超オンボロで、破れたシートがギシギシと音を立てながら走っていく。これでよく動くものだと感心する。おまけにほとんどの車がディーゼルであるため、町中が排煙に満ち満ちていて何処にいても臭い。国土が埃っぽいこともあって、外に長時間いると体に悪そうだ。
私はプチを拾った。メディナまでの料金を聞くと十五ディラハムだという。相場よりは高いようだったが、まだ勝手がわからなかったのでとりあえず言い値通り払った。その時はスムーズに英語が通じたが、それが珍しいケースであることは後になってわかった。
 |
左右を城壁に囲まれて延々と直線が続く「風の道」を散策し、非ムスリムでも入場を許される唯一の廟であるムーレイ・イスマイル廟へ入ろうとすると少年がやってきた。絵葉書セットを買えという。値段を聞くと二十ディラハムだった。絵葉書なら買っても良いかと思った私は十ディラハムに値切ってみた。すると彼は真剣な顔付きで封を開け、切々と訴えた。
「こんなに入っているんだから十五ディラハムまでしかまけられないよ。ほら、見てよ」
私はここを見た後で考える、と言い残してイスマイル廟に入っていった。こういう商売をする人は、必要性から英語を話すようだ。
中のパティオを抜けて礼拝室に入ろうとすると黒人青年がやってきて、料金を払えと言い出した。ここは無料のはずなのに、どういうことだろう。私が黙って相手の表情を窺っていると、彼がこう尋ねた。
「あなたは学生ですか?」
せっかく学生にみえるのであればわざわざ否定する必要もなかろう。
「そうだけど」
「では五ディラハムになります」
払うべき金なのかどうかはわからなかったが、その程度ならまあ許容範囲だ。ところが私が金を払うと、彼はヨーロッパからのグループと私とに向かって滔々と説明を始めたのだ。なんだ結局はガイド料か。しかもあろうことかフランス語だ。そんなことなら払うんじゃなかった。
イスマイル廟を出ると、果たせるかな少年が待ち構えていた。ところがそこへ親分格らしい中年が割り込んできて、絵葉書セットは二十ディラハムだと主張し始めたのだ。さっきこいつが十五だと言ったよ、と私がいうと親分は少年を叱り飛ばしている。君には悪いが、一旦十五と聞いたからにはそれ以上払うわけにはいかないのだよ。私は二十ディラハム札を渡し、しっかりと釣りを出させた。すると少年が私に尋ねた。
「あんたはどこの国の人?」
「日本人だよ」
「でもあんたは英語を話してるじゃないか。だから英語のガイドブックがいるだろ?これ、七十ディラハムで買ってよ」
彼はそう言ってなにやら本を取り出した。こいつ調子に乗っているなと思った私は、いらない、いらない、と言いながら、人差し指を左右に振るアラブ式のジェスチャーをして歩いていった。彼らはしつこくついてきたが、やがて諦めて去っていった。
このあともこの否定のジェスチャーは死ぬほど使うことになる。
 |
メクネスのメディナをどう攻めていこうか、と思案しながら広場でのんびりしていると、三十年配の男が寄ってきて世間話を始めた。向こうから話しかけてくる奴というのは例外なく英語ができる。モロッコ人というものに対してまだ何の警戒心も抱いていなかった私は、興味深く彼の話に耳を傾けた。
話が一息ついた所で彼が言った。
「ところで、時間はどのくらいあるんだい?」
時間ならたっぷりある。だがそう言ってしまうと面倒なことになりそうな気がした。
「うーん、実は二時間くらいで帰らなくちゃならないんだ」
「二時間か。だったら近くに父の店があるから案内するよ」
これがいわゆる「自称ガイド」(メディナ内の案内を受け持ち、高額のガイド料を取った上で自分がリベートの得られる店へ連れていって買い物させる、という連中)かとも思ったが、彼が、自分はガイドではないので金は要らない、ただ友達になりたいだけだ、他にも神戸や大阪に友達がいる、本当にただ友達になりたいんだけなんだ、としきりに強調するので、何も買うつもりがないことを伝えた上で付き合ってみることにした。
彼はガイドとしては非常に優秀で、次から次へと見どころを見せてくれた。初めて目にするメディナの中は、あらゆるものが新鮮で活力に満ち溢れ、そして古色蒼然としていた。
道行くジュラバ姿の人々、昼間からカードゲームに興じる男たち。奇声を発しながら水の入ったボトルを運ぶ洗濯屋、大きな積み荷を背負ってふらつきながら歩くロバと御者。肉屋の店頭で恨めしそうに目を剥いている牛の生首、縛られて道端に並べられギーギー鳴いている鶏たち。山と積まれた幾種類ものオリーブの実、無数の瓶に詰められた色とりどりの香辛料。裸で木彫をする男、雑貨を並べて売る女。石畳の回廊にはロバの糞が散乱し、ありとあらゆる商品の発する匂いと混じり合って異様な臭気が充満している。
彼は、ハンマム(アラブ式サウナ)の中やその炊き場、真鍮細工やタイルの手彫り工場、ござ作り、壷作りといった細分化された職人ごとに形作られた職工区である職人スークや、本来は非ムスリムは入れないであろう子供向けのイスラム教室などに案内してくれ、行く先々で職人から私宛てのちょっとしたプレゼントを貰ってくれた。由緒ある建造物の前ではそれがいかに古く、使われている色がどのようなものでどの都市に対応しているかなどについて熱弁を揮った。
これでは完全にガイドではないか。モロッコでは公認ガイドではないモロッコ人が外国人観光客と連れ立って歩くのは禁止されているはずなのだ。だがそのことを彼に尋ねると問題ないという。メディナの外には警官も多いが、メディナは彼らの城だ。メディナ内にいる限り身を守るすべがあるのだろう。
一通り見学すると、彼は絨毯屋に向かった。モロッコに行けば必ず一度は連れて行かれるという絨毯屋。店の主人(これが本当に彼の父であるかどうかは大いに疑わしいが)はつぎつぎに絨毯をひろげ、どれが良いかと聞く。私は買う気はないといって粘った挙げ句、店を出た。第一関門突破である。しかしそれ以降、彼はめっきり口数が少なくなってしまった。絨毯は高価なので、一発当てればリベートも大きい。それが外れたために不機嫌なのだろうと私は思った。
次に連れて行かれた真鍮細工屋も苦労の末脱出成功、続いて固形香料屋に連れていかれ、五ディラハムとの表示を見てこれなら、と購入を申し出た。何でもいいから安いものを買って、この際限ない巡礼を終了させる必要があったのだ。店員はケースから香料の塊を取り出して計量し、手早く包装すると澄ました顔で言った。
「百五十ディラハムになります」
「え、なにそれ?」
だがよくよく見ると五ディラハムの脇に目に見えないほど小さく"/グラム"と書いてある。ごねてはみたが埒があかない。これは迂闊だった。とんだ大出費だが、彼はこれでやっと満足したようで急に上機嫌になり、今度は私を食事に誘った。
 |
このままでは身ぐるみ剥がされそうだったので、もっと他にプレゼントは、とねだる彼を促して店を出、もう帰らなくてはと言った。のんびり食事をしているあいだに、外はバケツをひっくり返したような大雨になっていた。
「ホテルについていけばもっと何か貰えるかい?」
おいおい、勘弁してくれよ。ホテルにまでついてこられてはかなわない。
「悪いけどもう何もないんだ」
私は懇願するように言った。
「そうか、べつに問題ないよ」
そう言うと彼は雨の中に飛び出してグランタクシーを拾ってくれ、乗り込んだ私と握手をして別れた。
この国では握手は非常に重要である。知人と出会った際には必ず右手で(左手は直接尻を拭くのに使うので不浄と考えられている)熱烈な握手をし、抱擁し合い、時にはキスをする。この習慣は入国二日目にしてさっそく習得することができ、以降私は数限りない握手を交わすことになる。
さて、結局彼は何だったのか。どうやら悪い人ではなかったらしい。しかし相手の都合を考えずにいろいろな要求をするのには閉口した。だがそれがモロッコ人の国民性らしいと私が気づくのは、もっと後のことだった。
 |
ホテルに戻った私は、世界一の複雑なメディナを擁するといわれるフェズへ向かうことにする。さっきの大雨は一時的なものだったらしく、地面はいつの間にかすっかり乾いていた。私はアミールアブデルカーデル駅でフェズ行きの切符を買うと、夕刻、列車に乗り込んだ。
ところが列車は次の駅で停車したまま動かない。そういえば切符を買うとき、係員が四十五分とか言っていたな。これはフェズまでの時間ではなくて待ち合わせ時間のことだったかもしれないぞと思い、とりあえずその時間待ってみることにした。
しかし一時間待っても列車は動く気配がない。乗客はホームに降り立ちたばこを吸ったり駅員にかけ合ったりしている。だが降りているすきに列車が動き出してはたまらないので、私は車内でもう一時間待った。
動かない。いよいよおかしい。急なストライキだろうか。誰かに尋ねたかったが、コンパートメントにいるのは親子連れ、ジュラバの爺さん、冴えないおっさん、といった具合でとても英語は通じそうにない。アラビア語で尋ねるには例文集に載っているかどうか探す必要があったし、仮に載っていたとしても返答が聞き取れないのだから無意味だ。
覚悟を決めた私は荷物をまとめて列車を降り、情報の収集に努めた。しかし耳に入ってくるのはアラビア語のさんざめきばかり。小駅だけあって駅員に尋ねても英語を理解してくれない。言葉が通じない不幸をこの時初めて実感した。弱り果てた私は、ホームに出ている人に片っ端から聞いていくことにした。
「英語わかりますか?」
何人目かで、やっとイエスの声が返ってきた。声の主はモロッコ美人だった。フェズに住んでいるという。知的な風貌から見るに多分フェズ大学の学生だろう。早速何が起こったかを聞くと、大雨で洪水が発生し、列車が不通になったのだという。そこで復旧までの時間を尋ねてみたところ、驚くべき答えが返ってきた。
「二十分か数時間ね」
嗚呼麗しきはアラブの時間感覚かな。ちょっとレンジが広すぎるのではないか。私は今日中のフェズ行きを諦め、タクシーを拾ってメクネスに戻ることにした。さすがに明日になれば復旧しているだろう。