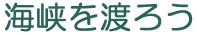
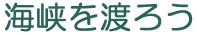
オトガルからメトロ(地下鉄)とトラム(路面電車)を乗り継いでスルタンアフメットに降り立った私は、後ろから流暢な英語で声を掛けられた。
「おや、君はバスで一緒だった日本人じゃないか。私を覚えているかね?」
振り向くと、良く言えば腕利きの営業マン、悪く言えば海千山千のペテン師といった風情の男がスーツを着て立っていた。
「え、バスで一緒?悪いけど覚えてません」
「なに、それも無理はない。まわりはみんなトルコ人だったからな。ベルガマからイスタンブールまでのバスに乗っていただろう。私も乗っていたんだよ。ところで君は何をしているの?」
「もう夜も遅いんで宿を探していたところです」
「宿ね。いくらくらいのところが望みかな?」
「うーん、百万くらい」
百万トルコリラは日本円で五百円にあたる。だが、そう言った直後に私はここがイスタンブールであることを思い出した。これまでのような感覚で宿を探すわけにはいかないのだ。
「あ、いや、二百万くらい」
「二百万ねえ…。二十ドルならいいところがあるんだが」
ちょっと高いかと思いつつも男についていくと、そこはオリベスク(古代エジプトの記念碑)の正面という絶好のロケーションのゲストハウスだった。私は主人と交渉して朝食付きで十五ドルにまけてもらうと、チェックインした。
「チェックインすることにしました。おかげで助かった。ありがとう」
「なあに、これで私にまた日本人の友人が一人できた。ぜひイスタンブールを楽しんでいってくれたまえ」
この場所で十五ドルというのが相場からいって悪くないものであることは後ほどわかった。大都会イスタンブールにおいても、トルコ人の親切は健在なり。
 |
翌朝早起きして開館前のブルーモスクの中庭を散策していた私に、中年のトルコ人が英語で話しかけてきた。いつものように型どおりの挨拶をしてこれまでの旅路を私が語ると、彼はモスクの歴史や柱に細かく掘りこまれた文字の意味などについて事細かに説明し始めた。
いくらガイドなんて必要ないと強がってみたところで、やはり地元の人に解説してもらえれば興味深いし理解も深まるものだ。私が感心して聞いていると、彼はアヤソフィアにまで案内してくれた。
私たちは公園のベンチで小休止を取った。
「おかげで大変ためになりました。どうもありがとう。ところであなたはどんな仕事をしているんですか?」
これまでの経験から、トルコ人というのは親切なものであるということを堅く信じて疑わなかった私は、他意もなく尋ねた。きっと彼も観光客を案内するのが趣味のような、暇なおじさんなのだろう。
「私か?私は絨毯屋だよ」
おお、ついに来た。絨毯屋だ。だが不思議にやられたという気はしなかった。はるばるトルコまでやってきて、絨毯屋の一人とも出会わずに帰ったのでは面白くないではないか。
良かったらうちの店に来てみないか、という彼の誘いに、私は乗ってやることにした。
シックな絨毯屋だった。古い建物を改装したのだという店舗は一見新築のようで、いくつかの絨毯がまるで一級の芸術品のように、互いの主張を侵害し合わない範囲で飾られていた。悪くない店だと私は思った。
 |
「どうです?きれいでしょう」
「いいですね」
「もう絨毯は買いましたか?」
「残念ながら買ってしまったんですよ」
「え、どこで?」
彼は心底残念そうな顔で尋ねた。
「イズミルで」
「それはウールでしたか、それともシルク?」
「ええっと、確かウールでしたね。もう日本に送ってしまいましたが」
「幾らで買ったの?」
「それはちょっと…」
「いいから。値段を聞けばだいたいわかります」
「値段、値段と。いくらだったかなぁ。確か二億トルコリラ(十万円)くらいだった」
「それは高い。あなたは騙されていますよ。ウールでそんなに高いものはない。柄はどんなでした?」
「え、柄?柄は…あそこに飾ってあるような奴です」
私はだんだん追い詰められてきた。そもそも買ってもいない絨毯の値段や柄なんてわかるはずがないのである。でもここまできたら嘘をつき通すしかない。
「ではシルクの絨毯を一枚いかがですか?」
「シルク?シルクの絨毯はモロッコで買ったからもういらないんです」
もう少し手応えがあるかと思っていたが、あっけなくゲームセットであった。トルコの絨毯屋、恐るるに足らずだ。
私は一旦宿に戻ると朝食をとり、新市街へと向かうことにした。昨晩ここへ来たときと同じようにトラムに乗っていってもよかったのだが、せっかくのいい天気でもあり、のんびりと歩く方を選んだ。
線路は細い通りを縫うように走り、その上を人も車もトラムも通る。古い町並みの中、横丁をひやかしたり小高い丘に上ったりしているうちに、私は旧市街と新市街とをむすんで金角湾にかかる長大な橋、ガラタ橋までやってきた。
ガラタ橋は観光客にとって重要である以上に、イスタンブールっ子の生活とも密接に結びついている存在である。
袂では小船に乗った威勢のいい男たちが名物鯖サンドを売っている。せわしげに通り過ぎて行くビジネスマン、不思議な道具を実演販売する的屋、客足の引きも切らないとうもろこし売りの屋台、そして駈け回る子供たち。
橋の上では太公望がずらり並んで釣り糸を垂れ、衣類商が路肩に座ってシャツやパンツを広げている。車の流れは絶え間なく、通勤船や観光船がゆったりと行き交う。
ありとあらゆる種類の人々を抱擁して養っていく、懐の深い大都市の姿がそこにはあった。私は太い欄干にもたれ、ボスポラス海峡を眺めた。さっきから一人の客もつかない老眼鏡屋も、頭にパンのいっぱい入った盆を載せてふらふら歩き回っている男も、顔つきには悲壮感がなかった。
きっとここはいいまちなのだ。人々の目が、表情がそう語っていた。
 |
新市街の喧騒を楽しみ、旧市街へと引き返すために再びガラタ橋を渡っているときのことだった。ちょっとした人だかりを見つけた私はその輪の中に入っていった。そこでは一人の男がショーをやっていた。だがよく見ると、それは賭博だった。
ルールは簡単だ。同じ色と形をした鉛筆大の四本の筒があり、そのうち一本だけは振ると音が出る。胴元が最初に当たりの筒を提示し、その後かちゃかちゃと何回か筒の位置を組み替える。そして客はどの筒が当たりかを指差した後、トルコの最高額紙幣である五百万トルコリラ(二千五百円)を賭けるのだ。胴元はその筒を持ち上げて振り、音がすれば倍返し、しなければ没収である。
まわりのトルコ人たちは我先にと争って賭け、そしてその殆どが負けていた。私には俄かに信じ難い光景だった。私は今まですべてを当てていた。私が心の中であれが当たりだと思った筒は、必ず当たりだったのだ。
こんな簡単なことがどうしてわからないんだ。もしかして日本人とトルコ人とでは動体視力が違うのだろうか。
「日本人、どうだい賭けないか?」
賭けたいのは山々だった。もし最初から賭けていれば、今ごろ今回の旅行費用くらいは軽く稼げていたはずだ。だが悲しいかな帰国を明日に控え、財布の中には四百万ほどしか残っていなかった。
「金がないんだ、やめとくよ」
私はその場を去った。まあトルコまで来て博打もないだろう。おとなしく帰るのが身のためだ。しかし頭ではそう理解できていても、体の芯がいうことをきかなかった。
あそこまで確実な儲け話を棒に振るというのはいかがなものか。事実、私は一つとして、そう、一つとして外しはしなかったではないか。五百万さえあれば、何の苦労もなく小金を手にすることができるのだ。
いつしか私は小走りになっていた。まちに戻って金を都合しよう。
これまで自分には無用のものとして目障りな存在でしかなかったキャッシングマシーンが、急に救いの神に思えてきた。ドンドルマ(アイスクリーム)屋の前で機械を見つけた私は、静かにビザカードを差し込んだ。
五百万トルコリラ。
金額を指定して暗証番号を打ち込むと、機械音とともに一枚の紙幣が吐き出された。私には一枚あれば十分だ。負けるはずがないのだから。
クレジットカードを持つようになってから十年間、一回もやったことのないキャッシングをよりによってトルコでするとはね、と私は思った。
私は小躍りすると札を掴み、ガラタ橋へと走った。だが中央の橋脚を通りすぎ、しばらく行ってもさっきの人だかりはなかった。行き過ぎてしまったのだろうか。今度はゆっくりと歩いて戻ってみたが、やはりどこにも彼らの姿はなかった。
気が抜けた。右手の中で、五百万トルコリラ札はくしゃくしゃになっていた。
 |
頭を冷やしてよく考えてみたら、立ち去ろうとする私に百ドル札で賭けるよう誘い掛けてきたのも怪しければ、あれほど簡単な技に誰もが次から次へと撃沈されていったのもおかしい。もしかして胴元と観客がグルになって仕組んだ、外国人狙いの詐欺だったのではないだろうか。
そう考えればすべて納得がいく。金払いのいい外国人をちょっとだけ勝たせ、いい気になって掛け金を吊り上げたところで彼らの「本当の技」を使って一気にへこませるのだ。
なるほどね。私は自分の考えにすっかり感心し、それでも掴み損ねたチャンスを少しだけ惜しみながら、一人帰路についた。
イエニ・ジャミイに群がる世紀末的な鳩の大群に驚き、スカーフを被った女性たちでごった返すエジプシャンバザールを抜けると、すでに日は沈みかかっていた。イスタンブールの一日が終わろうとしている。
私はエミノニュ桟橋に向かうと、ハレム行きの船を選んで乗りこんだ。出港を知らせる霧笛が鳴り響き、家路を急ぐ人々を乗せた中型のフェリーはゆっくりと桟橋を離れた。
甲板に立ってまちを見渡せば、赤く燃える夕陽に、ブルーモスクが、アヤソフィアが、ドルマバフチェが映えていた。肌を刺す潮風は、このまちに急速に冬が訪れつつあることを告げていた。
無機的な通勤船には一日の仕事に疲れた労働者たちの哀愁が漂っており、いよいよ沈まんとする太陽には私たちを暖めるだけの力はすでになかった。
群からはぐれたかもめが一羽、寂しそうに上空を旋回していた。