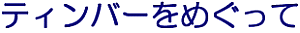
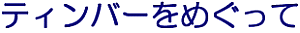
朝八時半に私はプチでフナ広場に向かった。
その頃には私は、観光客にはメータを使わないとされるモロッコのタクシーにメータを使わせる方法を独自に会得していた。乗り込むや否や、足下のメータを指差して、カウンタ、カウンタ、と叫ぶのである。すると大抵、ウイ、ウイ、と答えてメータのスイッチを入れてくれる。後は行き先を言うだけだ。料金交渉の手間も省けて一石二鳥。
 |
 |
コーヒーショップのそばにはいくつもの店があった。署を出た私は、まずは煙草屋に入ってみた。私が紙を渡すと、主人はなにやら言っている。紙がフランス語だったためか、フランス語をしゃべっているようだったがよくわからない。少なくともここには置いていないことは確かなようだったので次に隣の写真屋に行ってみた。おやじは紙を見て、「ポステ」だといっているようだった。そうか、切手か。きっと明日以降に出来上がった申告書を郵送してくれるに違いない。
だが郵便局に行った私はなぜかそこでも拒否にあい、八方ふさがりになってしまった。局員は「タバッコ」と言っていたようだが、煙草屋ならさっき行った。
いい機会だから逃げ出そうか、とも思った。だが今や意地でも申告書を手にしなくてはならなかった。たかだか数千円の時計に免責三千円の損害保険を適用したいがために入手するのではない。この短い日程の中、事件の処理に足掛け二日も費やしている。ここでおめおめと引き下がるわけにはいかなかったのだ。
私がカフェで途方に暮れていると、男が、ハイ、ジャパン!と声をかけてきた。本来ならもっとも黙殺すべき種類の人間であったが、今はとにかく英語の通じる相手と話したかったので、そいつに掛け合ってみた。すると彼はもう少し英語の分かる人をつれてきて、その男が案内してくれることになった。
最初に行ったのは郵便局である。そこには欲しいものはやはりなく、次に彼は私をさっきとは別の煙草屋に連れて行き、私はそこで遂に二十ディラハムのティンバーを手にすることができたのだ。ティンバーとは、印紙のことであった。
彼がにこやかに去っていこうとしたので私は急いでチップを渡した。こんな街で純粋な親切に出会えると、やはり嬉しいものだ。
私が印紙をもって帰ると話は俄かに展開しだし、あっという間に申告書が出来上がった。だが時は既に十一時、列車の出発まであとわずかな時間を残すのみだった。
 |
私はメディナの見納めにと、地元市民の生活の場となっている日用品を売るスークを訪ねた。そこでも私は市井の人々と触れ合うことができた。
こうしてみるとこの国も悪くはないな。フェズですっかりすさんだ私の心、この国への嫌悪感は、マラケシュの人々によってだいぶ解きほぐされていた。
メクネスやフェズで出会った連中も、物事の考え方が我々日本人とは異なるだけで、根はいい奴らなのかもしれなかった。私は母国とはまったく異なる文化の中にもっと溶け込むよう努力すべきだったのだ。だがそれはとても難しいことでもある。
盗難に遭い、お役所仕事に振り回されたこの二日間ではあったが、心は穏やかだった。一週間を振り返るとさまざまな出会いと別れ、正直と欺瞞、そして下心と親切とがあった。どれもこれも一人旅ならではの経験だったと思える。
またいつかこの国に来ることがあるだろうか。多分ないだろう。私はいい思い出とそうでないものとを胸に、一路カサブランカへと向かった。帰国すればきっとすべてが懐かしく思い起こされることだろう。その日まで、あと三日であった。